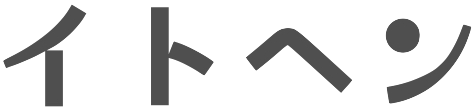鷲ぬ鳥節[ばすぃぬとぅるぃぶすぃ]
綾羽ば生らしょうり びるぱにばすだしょうり
——
バスィヌトゥルィヨウニガユナバスィ
玉代勢長傳編『八重山唄声楽譜付工工四全巻』2006年、pp.19-20(初版『八重山唄工工四全巻』1971年)
次に習ったのが「鷲ぬ鳥節」だ。八重山民謡の定番中の定番、催しの座びらきに唄われることも多い唄である。コンクール(といっても、演奏の優劣を競うのではなく、昇級試験のようなもの)の新人賞の課題曲の一つでもある。
「でんさ節」と比べても、三線の弾き手が難しいことはない。メロディも唄いにくいことはない。この曲で難しいのは、「島むに」(島のことば。とくに八重山を強調して「やいまむに」ともいう)の発音だ。
タイトルからして激しい。漢字をそのまま読んではいけない。バスィヌトゥルィブスィである。小さいイやウが頻発して口が忙しい。日本語の標準語と比較してみると、「わし」→バスィ、格助詞「の」→ヌ、 「とり」→トゥルィ、「ふ(ぶ)し」→フ(ブ)スィ。日本語と似たところがあるような、発音の違いに法則があるような、ないような……
例えば「し」をスィにするには、シとスの間の音を出す。同様に「り」をルィとするには、リとルの間の音を出す。それでは、イ音はイとウの間に変換して発音すればいいのかといえば、そう簡単な話ではない。冒頭の歌詞の「あやぱにば」の「に」はニ、「びるぱにば」の「び」はビ、「に」はニなのである。
さらにそれに続く歌詞、「すだしょうり」の「す」は、漢字で表記すると「産」なのだが、これの発音はスィ。あれれ、今度はウ音がウからイに寄っちゃったよ、と頭を抱えたくなる。
想像するに、教本である『八重山歌工工四全巻(八重山古典音楽安室流保存会)』がまとめられた1971年ごろは、あえてスィだのルィだのと表記しなくても、八重山の人なら自ずと単語ごとにシ/スィ/ス、リ/ルィ/ルを区別していたのかもしれない。でも他所者のわたしたちには死活問題である。レッスンで新しい唄を習うたびに、「ここのスはスィに直して」「ルじゃなくてルィ」などと師匠が指摘するのを一箇所ずつメモしていくしかない。
これが延々と続くのかと、最初は暗澹たる思いがしたものだが、歌詞に使われる語彙はそれほど多くなく、また歌詞にはパターン化されてよく使われる言い回しもあるので、なんとか覚えられなくもない量である。八重山育ちの人でも若い世代となると、発音が難しくなっているところもあるようなので(コンクールの講評でしばしば発音が指摘されるので)、これからはわたしたちだけの問題でもないのかもしれない。
さて、じつはスィでさらに衝撃的だったのはこの先である。仮名だけ見ると、スの口の形でシと発音するか、あるいは反対にシの口の形でスと言うのか、そのどちらかなのだろうと見当をつけたくなる。というのも、わたしは大学時代、第二外国語は中国語を選択したのだが、ピンインと呼ばれるローマ字で表音した中国語で [si] とあるときは、後者の方法、つまりシの口の形でスと発音するといいと習っていたのだ(日本語母語話者にとって発音しやすい方法というだけで、厳密には違うかもしれない)。
しかし、である。師匠が「スだと、口を丸く突き出したウの形になるけれど、それではダメです。シでもありません。スィ」と披露された口の形は、口の左端が閉じて右端が半開きなのである。右端の薄い隙間から、スィの音が絞り出される。歪んだ口に、師匠の強い目力が相まって、その様はまるで不動明王。にらまれながら吐き出されるスィ。
とてもではないが、できない。わたしは人前で不動明王にはなれない。どうしたらいいんだ。と悩む暇もなく、陽気な師匠が「みんなで言ってみましょう。スィ」。続けて生徒が「ス」。「違います。もっと口を引いて、スィ」「シ」「シになっています。シでは口を引っ張り過ぎ。スィ」「スイ」「だんだん良くなってきました。スィ」「スィ」のような練習が今日も繰り返されるのである。
この不動明王問題。スィ、ルィだけでなく、クィ、ツィなどでも起こる。八重山の人のなかでも、口を半開きにする人としない人がいることは、後々知ったのだが、東京で日常的に会えるネイティブスピーカーは師匠だけだ。八重山らしい発音に近づくには、師匠から正しい音を聞き、口の形を真似するしかない。
一応、師匠の名誉のために附言すると、師匠が不動明王になるのは、ことさら発音を覚えさせようとするときだけであって、唄っている最中は目力はそこそこ、にらみ顔にはなっていない。口は歪んでいるけれど。