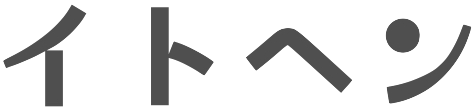「崎山節・崎山ユンタ〈コロナ禍に唄いたい3〉」でも触れたが、崎山節の高低を繰り返すメロディーは胸を締め付けられるような悲しみが表れていて、うまく唄えるようになりたい気持ちをかき立てられる。唄の舞台である西表島の崎山村は、琉球王府の時代に強制移住によって開拓され、のちに廃村している。そんな八重山らしい悲劇性もまた、唄いたい気持ちを後押しする。
崎山節を調べていくと、早々に検索で当たるのがこの本だ。1903年に崎山で生まれた川平永美氏が、崎山を回想して語っている。崎山村は1948年に廃村、川平氏はその3年前に隣の網取村に移り、1957年に石垣市登野城に転居、定年退職後からふるさとについて語り出し、2000年に98歳で亡くなった。崎山最後の語り部なのだが、その記憶力の豊かさには感嘆する。この聞き書きをもとに映像化できるんじゃないかと思うほど。
そうした数々の崎山についての証言は必見なのだが、本書の主題に入る前の、川平氏が自分の出生を語ったページで、まず目が釘付けになってしまった。川平氏の母親は「賄女(まかないおんな)」だったのだ。
琉球王府時代、八重山を統治するために首里から派遣された役人たちは、妻を伴うことはなく、八重山の女性を現地妻とした。現地妻を賄女という。村一番、島一番の美女が賄女にされたのは言わずもがな。賄女になると、その後の生活の心配がなくなるので、ステイタスだった面はあるのだが、貧乏な親が泣く泣く娘を差し出したり、恋人がいても引き裂かれたり、という話は民謡のモチーフになっている。また、賄女が産んだ子が、赴任が終わって首里に戻る父に連れていかれるケースもある。それをまあ、飯炊きのお手伝いさんみたいな名称で呼ぶなんて、現代っ子のフェミなわたしには腹が立つばかりだ。
そんな賄女。ものすごく昔の話だと思っていたのに。この本のための調査は1974年に始めたそうで、偶然にもわたしが生まれた年なのだが、つまり賄女の直系が同時代を生きていたことに驚かずにいられなかった。
といっても川平氏は明治生まれ(1903年=明治36年)だから、川平氏の両親も民謡で謳われたままの役人-賄女ではない。すでに琉球王府はなく、沖縄県だったのだが、1903年まで琉球王府時代の悪税である人頭税が続いていて、川平氏の父親はそのために崎山に派遣されていた役人だ。首里からではなく、石垣島から派遣され、石垣と崎山を行ったり来たりしていたという。行ったり来たりしていたのに、現地妻がいるとは、トホホ。そして父は任期が終わると、川平氏の兄だけを連れて石垣に帰り、母親と川平氏は崎山に残された。これまた昔通りで、トホホ。
母はその後、再婚し、川平氏は母方の伯父の下で幼少期を過ごし、学校には伯父宅のほうが近いため、伯父宅から通い、週末だけ母と過ごしていたようだ。とまあ、そんな小学校時代から回想が始まっていく。
働き始めてからは、貴重な現金収入源として村をあげて取り組んでいた香木(沖縄の線香の材料になる)の事業に携わり、伯父が建てた赤瓦を焼く工場で下働きをし、炭鉱間を巡る船の船員にもなった。西表島の近代のトピックを渡り歩いているような前半生なのだ。
川平氏の語りは、本書と同じ編者によって、『島からのことづて 琉球弧聞き書きの旅』(2000年、葦書房)、『西表島の農耕文化 海上の道の発見』(2007年、法政大学出版局)にもまとめられているそうなので、近々入手して、もっと真面目に崎山に向き合ってみたい。今回は賄女に気を取られすぎた。
| 書誌情報 『崎山節のふるさと 西表島の歌と昔話』 著:川平永美 編:安渓遊地、安渓貴子 発行:ひるぎ社(1990年7月) おきなわ文庫(2012年9月に電子書籍として復刻) 2020年に電子書籍版をKindleで943円で購入 |